2003年度 中国文芸研究会総会議案
(於2003.4.29 白雲荘)
*会員数は278名(2003.4月現在)と昨年減少した分を取り戻し、一昨年レベルを維 持している。新規加入は大学院生を中心とする若手層である。こうした若手層は一定 研究会の例会や合宿に参加してきており、研究会活動における活躍が期待される。 3-40歳代の例会参加が少なくなっており、2-30代の若手の積極的活動に負うところが 大きくなっている。
*運営面では、事務局の役割分担を明確にして、 順調に研究会活動が展開されたと 考えられるが、今後、さらに事務局の役割(分担体制と全体の調整など)を実践的に 工夫していくことを通じて、実務や運営を直接的に担う会員を増やし、研究会の活性 化につなげていく必要がある。Mbr. *以下、各事業項目に従って活動状況を報告する。
(1)『野草』刊行について
*第70号 (2002年8月1日刊行、編集担当:松浦恆雄、版下作成:平坂仁志)および第 71号(2003年2月1日刊行、編集担当:福家道信、版下作成:平坂仁志)を予定どおり刊 行することができた。「『野草』編集の手引き」によって、編集作業をマニュアル化 したことで、編集事務を効率化できたと考えられる。
*第70号は、途中で編集担当が交代することになり、やや編集事務が遅れることに なったが、内容的には、一定の水準が維持できた。第71号は編集初挑戦の福家先生に お願いしたが、「『野草』編集の手引き」に基づいて、無事刊行することができた。 「手引き」の内容については、継続的に検討していかねばならない。
*関西在住の会員に限らず、例会・夏合宿で報告・討論の後に『野草』に執筆すると いう方向性は、この間、ほぼ定着してきている。
(2)『会報』発行について
*和田知久・好並晶・藤野真子・永井英美・井上薫・上原かおりの6名の編集担当者 の努力によって、第246号(4月)~第257号(3月)まで順調に発行した。遠隔地在住 者による編集も、コンピュータネットワークを用いた協力体制により定着した。
*運営事務の簡素化のため、12頁を限度とすることはほぼ定着した。投稿を増やしつ つ内容充実と多様化を図ることは、近年来の課題として今後も引き継がなければな ない。「交流」は、 会員の意識的努力とコンピュータネットワークの活用によって 収集する形態が定着したが、情報提供者に偏りがあり、内容的にも改善されていな い。会員の自覚的な情報提供に加えて、組織的な情報収集が求められる。「例会」記 録は、報告者によるレポートという形が定着した。
*250号は249・250・251号合併の記念号とした。34名の執筆者と会報担当者の努力に より、140頁を越える充実した号となった。
*誰でも気楽に投稿できる、機動性のある研究情報誌としての『会報』のあり方を更 に工夫していくことが課題となっている。
(3)「例会」開催について
*予定通り年間10回の「例会」を開き、参加者も毎回ほぼ一定していた。関西以外の 遠方からの参加者が少なくなかったのは喜ばしいことである。例会参加者には、若手 層が増えている反面、研究会歴の長い会員やベテラン層の出席が減少している。若手 層、新入会員の例会での積極的な発言や他の活動への参加が期待される。
*研究発表は、『野草』投稿希望者によるものが半数を上まわり、「例会報告→『野 草』掲載→例会での合評」というサイクルが定着しつつある。内容も充実したものが 多く、学会発表に伍しうるものもある。また通常の研究発表の他、4月例会で古典分 野の講演を、12月例会で、『中国文芸研究会会報 第二百五十期記念号』の合評を 行った。後者は初めての試みで、有意義な内容との好評を博した。
(4)「夏期合宿」について
*担当者(鈴木康予・西村正男)の企画により、8月28~30日の3日間にわたって徳島 県鳴門市「民宿鳴門」において開催された。参加者はのべ18人と、例年より若干減少 した。内容的には、書評、『野草』関連と充実したものであった。民宿の食事は値段 のわりに海の幸が充実しており、好評であった。鳴門市ラーメンツアー、ドイツ館、 鳥居龍蔵記念館なども興味深かった。
(5)「野草基金特別事業」関係について
*「野草基金」を用いて、『今天』復刻版を再発行した。販売は内山書店に委託し た。内山書店からの報告によれば、現在100部のうち、23部が売れたとのこと。滑り 出しとしては快調とはいえないが、『今天』に広告を掲載するなどの措置を内山に依 頼している。『野草』「会報」で広告宣伝活動も行っていく。
(6)「野草ネットワーク」について
*ホームページは、菅原慶乃を中心とし、ホームページ更新作業を担当してもらうよ うになり、内容充実を図った。画面が整理工夫され、見栄えのするものになった。
URLは http://bluesky.osaka-gaidai.ac.jp/~bungei/bungei.shtml
*「野草掲示板」の再構築については十分討論できず実現しなかった。
*「会報」のHTML化も実現しなかった。
*「野草メーリングリスト」は会員交流の場として、「事務局メーリングリスト」は 実務作業効率化の手段として、重要な役割を果たしてきたが、「野草メーリングリス ト」はあまり活発ではない。気軽な意見交換の場として、活用されることが望まれ る。
Ⅱ.2003年度活動方針
*運営体制をさらに工夫し、研究会の全般的活動の水準維持と向上につながるように 努力しなければならない。
*引き続き、事務局の仕事を合理化し、明確な分担体制を確立し、各種活動が連係し あえるように円滑な運営を図ることが必要である。
*その際には、大学院生を中心とする若手層および関西以外の会員にも主体的・積極 的な参加と具体的な役割の分担をよびかけたい。活動の工夫を続けるとともに、若手 層の自主的積極的取り組みも歓迎したい。
1.各種研究活動について
(1)『野草』刊行
*会員の研究成果を公表する場として常時機能するように誌面を工夫する。「特集」 中心にするか、投稿中心にするか、などは編集者の裁量にゆだねる。なお、編集作業 においては、「『野草』編集の手引き」を活用し、締切り厳守の徹底により、「原稿 審査(査読)」、版下作成を含む全ての編集作業を円滑に進める必要がある。
*「例会報告→『野草』論文掲載→例会における合評」という流れを原則とする。 『野草』編集担当者は、特集テーマを早期に決定し、執筆者と連絡を密にして、上記 の流れがゆとりをもって進行するようはかる。
*当面の発行計画は以下の通りである。
第72号──2003年3月末締切、2003年8月1日刊行予定。編集担当:三須祐介
第73号──2003年9月末締切、2004年2月1日刊行予定。編集担当:西村正男
特集テーマ:「文壇史の脱構築/再構築」
第74号――2004年3月末締切、2004年8月1日刊行予定。編集担当:未定
*原稿の応募・投稿は、以上のスケジュールを会員に周知徹底したうえで、締切を厳 守して頂くことを条件とする。
(2)『会報』発行及び発送
*和田知久・好並晶・藤野真子・永井英美・井上薫・上原かおり・佐原陽子・三須祐 介の編集担当体制によって発行する。
*内容の充実・活性化をいっそう図っていくことが課題である。この間、若干弱まっ ている「交流」欄を充実させる必要がある。事務局でも工夫を図るが、全国の会員の 皆さんも、「野草メーリングリスト」などを活用して研究情報を寄せていただくよう お願いしたい。また「書評の会」で提示された書籍を会報上に紹介するよう工夫す る。
*「例会」記録は原則として、「例会」の発表者に執筆をお願いする。海外留学者と 連絡を密にし、現地レポートを書いてもらえるようにする。海外留学者はEメール・ メーリングリスト等を通じて現地レポートを寄せるように努力されたい。
*編集担当者・〆切・原稿送付先は以下の通り
| 号数 | 〆切 | 編集担当者 | 4月号 | 3月末日 | 永井 |
| 5月号 | 4月末日 | 井上 |
| 6月号 | 5月末日 | 上原 |
| 7月号 | 6月末日 | 和田 |
| 8月号 | 7月末日 | 好並 |
| 9月号 | 8月末日 | 藤野 |
| 10月号 | 9月末日 | 永井 |
| 11月号 | 10月末日 | 井上 |
| 12月号 | 11月末日 | 上原 |
| 1月号 | 12月末日 | 和田 |
| 2月号 | 1月末日 | 佐原 |
| 3月号 | 2月末日 | 三須 |
原稿送付先
郵送の場合:〒562-8558、大阪府箕面市粟生間谷東8-1-1、大阪外国語大学青野研究室気付、中国文芸研究会事務局宛
Eメールの場合: 中国文芸研究会事務局bungei@aonoken.osaka-gaidai.ac.jp まで
原稿は、原則としてフロッピィ入稿にプリントアウトを添付(外字部分を明記)す ることとし、返却は行なわない。ただし、原稿・写真などの返却を希望する場合は、 その旨を申し出て、返信用封筒(切手添付)を同封することとする。なお、Eメール による入稿も可であるが、その際も別便でプリントアウトを郵送するのがのぞまし い。
*海外研究機関・研究者への贈呈及び海外留学者への配送サービスのあり方について は引き続き検討する。海外発送担当者は好並晶とする。
*会報のページ数は当面最大12ページとする。原稿の採否は編集者の判断でおこな う。 *発送に必要な封筒・糊などの文房具は、会場(大阪経済大学谷研究室または白雲 荘)に備え置く。
*会報をメールマガジン化し、ユニコードによる簡体字、繁体字、日本語混在のHT ML形式を採用する。希望者にはメールアドレスを登録してもらって、定期的に(毎 月)発送する。なお会報はメールマガジン2号分をまとめて、ミスタイプなどを修正 の後、印刷にまわし、偶数月または奇数月にクロネコメール便で発送する。(印刷と 発送作業は隔月)
(3)「例会」開催 *「例会」の開催は、例年通り、7、8月を除き、年10回とする。各月最終日曜=午後 1:30開会。また、12月は忘年会を兼ねるため、日時を別に定める。
*講演(会員外・他領域・外国人研究者などを含む)・書評を年間各1回程度、『野 草』の「特集」テーマに関する報告を数回行うこととする。研究発表希望者は、調整 を必要とする場合もあるので、早めに担当者まで申し込むこと。コメンテイターにつ いては発表者の申し出によって相談する。
*『野草』合評会の討論内容は、次号の『野草』誌上に掲載する。論文執筆者は合評 会に出席することを原則とする。
*「例会」担当係は、北岡正子とし、例会の企画と報告希望者の調整を担当する。
*具体的スケジュール(「例会」カレンダー)、及び現在決定している報告予定者な どは以下の通り。なお、単純計算では、通年14回の発表の機会があるが、随時、『野 草』の「特集」関連報告、講演・書評などが入る。現在のところ、夏合宿では「特 集」関連の企画をも組み込んでいる。
| 月 | 報告一 | 報告二 |
| 4月 | 講演:弓削俊洋 | 総会 |
| 5月 | ★中野知洋 | ★藤澤太郎 |
| 6月 | ★星名宏修 | 永井英美 |
| 7-8月 | 「夏期合宿」 | |
| 9月 | 『野草』72号合評 | |
| 10月 | ★? | 未定 |
| 11月 | ★? | 未定 |
| 12月 | 忘年会(講演・書評など) | |
| 1月 | 未定 | |
| 2月 | 未定 | |
| 3月 | 『野草』73号合評 | |
(★『野草』特集関係)
会場は、偶数月は白雲荘(京都会場=京都市上京区寺町上立売上ル2筋目西入ル Tel 075-231-1320)とし、奇数月は大阪経済大学(大阪会場=大阪市東淀川区大隅 2-2-8)とする。ただし、1月例会は、入試の関係で会場変更になる可能性がある。 会場の予約は偶数月会場の白雲荘に関しては宇野木洋を、奇数月会場の大阪経大に ついては谷行博を予約の担当とする。二次会の会場予約担当は、宇野木洋とする。 発表希望者は、例会担当:北岡正子まで直接電話で申し込む こと。
(4)「夏期合宿」開催
*集中的な研究交流の場として、今年度も「夏期合宿」を実施する。テーマ・報告者 ・場所などについては、合宿担当:黄英哲・鈴木康予を中心に具体化を図る。
*「夏期合宿」は以下のように二案を平行して用意する。第一案を優先的に準備しつ つ、SARS問題の動向を見守りながら、第二案にするかどうか決定したい。
日時:第一案 8月26日-29日 第二案 8月27日-29日
場所:第一案 台湾陽明山 第二案 高野山
内容:第一案 朱天文または朱天心を囲む会・中央研究院中国文哲研究所訪問=楊 牧所長との座談会。胡適記念館見学、当代台湾文学資料センター訪問、その他、第二 案 書評、個人発表、『野草』75号関連
Mbr> (5)「書評の会」
*「書評の会」は、偶数月京都会場のときに「例会」前の午前中という日程で実施し ていくが、引き続き運営のあり方も検討する。運営担当は松浦恆雄とする。
(6)「特別事業」計画
*研究会の事業として、宇野木洋を中心に、 『図説中国20世紀文学』(白帝社)の 改訂作業を行う。
(7)「野草ネットワーク」
*コンピュータネットワークを利用した『会報』『野草』の編集の効率化は実現・定 着した。コンピュータネットワークは、単に事務の効率化に留まらず、遠隔地との交 流や種々の情報提供・発信手段としても、大きな可能性を持っている。それを全ての 会員のものとするために、インターネットの普及なども視野に入れつつ、今年度も引 き続き実践的に検討を深める。担当は青野繁治・菅原慶乃とする。
*『野草』掲載論文の検索を始め、本研究会に関する様々な情報を発信している 「ホームページ」( http://bluesky.osaka-gaidai.ac.jp/~bungei/bungei.shtml )を、いっそう豊かな内容に充実させていく。特定の個人への負担を軽くするた め、ホームページの管理を「野草」「会報」「例会」「記録」「その他」など項目毎 に分担することが望ましいが、今後、青野繁治・菅原慶乃を中心に、項目毎の担当者 を募集し、管理の仕方を検討していく。
*「野草メーリングリスト」(加入及び脱退に際しては、ネットワーク担当の青野までメールでアドレスを知らせることで加入手続きを行 う)を活用した会員間の交流にも期待したい。特に論文・著書などを書かれた方は、 メーリングリスト等を通じて、題名、発行所、年月日などをお知らせいただけるとあ りがたい。
*「電子掲示板」設置を検討する。サーバへの負担軽減のため、プロバイダ等が提供 する無料掲示板を利用し、研究会ホームページにリンクすることを検討する。
2.運営体制について
*研究会の運営は、事務局、『野草』編集委員会及び運営委員会によって行う。若手 層の参加を推進して、再編・強化を図る。
(1)事務局
*事務局の住所は以下の通り。
〒562-8558 大阪府箕面市粟生間谷東8-1-1 大阪外国語大学 青野研究室気付
電話とファックス:0727-30-5245
E-mail:
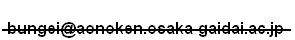
*事務局は、総会決定に基づき、『会報』編集・「例会」開催・『野草』印刷などの 日常的な実務を担当する。仕事と担当者は以下の通り。
*「例会」担当:北岡正子、会計担当:今泉秀人、『野草』印刷担当:平坂仁志、 『野草』編集担当:三須祐介・西村正男、『会報』編集担当:和田知久・好並晶・藤 野真子・永井英美・井上薫・上原かおり・佐原陽子・三須祐介、「夏期合宿」担当: 黄英哲・鈴木康予、MLサーバ管理担当:青野繁治、ホームページ担当:菅原慶乃、 「特別事業」担当:宇野木洋、組織(会員名簿管理・タック印刷)担当:藤野真子、 刊行物海外発送担当:好並晶、によって事務局を構成する。なお事務局運営の幹事長 は青野繁治とするが、幹事長不在の場合、宇野木洋または松浦恆雄が幹事長代行とし て運営を遂行する。
(2)『野草』編集委員会
*『野草』編集委員会は、『野草』の編集・刊行全体に責任を持ち、また「原稿審査 (査読)」のあり方などを始め、中長期的な課題について検討を行なう。2003年度 は、青野繁治・平坂仁志・藤野真子・北岡正子・松浦恆雄・太田進・斎藤敏康・谷行 博・宇野木洋・和田知久・好並晶・福家道信及び『野草』編集担当の三須祐介・西村 正男によって構成する。
*『野草』編集委員会は、必要があれば、参加者を拡大して開催することができる。
(3)運営委員会と会計監査
*運営委員会は、事務局で処理が困難な問題が生じたり、長期的・大局的な観点が必 要とされる場合に、運営委員長の責任において開催され、問題の処理にあたる。その 構成は、太田進(運営委員長)・筧文生・岡田英樹・阪口直樹及び事務局構成メン バーとする。
*財政の健全な執行を図るべく、会計監査役を置く。会計監査役は橋本草子とする。
(文責:青野繁治)